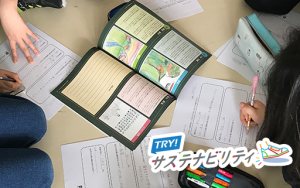※本記事は7月20日時点の情報です。
パーソルイノベーション株式会社は、2021年5月から、アクティブシニアと企業の“共創マッチング”サービス「アライクワーク」β版の提供を開始しました。
●アライクワークとは
「アライクワーク」は、アクティブシニア(就労意欲のある60歳以上のシニア)と人材不足に悩む企業の仕事をオンラインでマッチングするサービスです。
仕事を通じてやりがい・生きがいをもって社会と繋がるシニアを増やすとともに、地域のシニアと企業が力を合わせながら地域社会を発展させていく「地域共生社会」の実現を目指しています。
サービス提供開始にあたり、第一弾として、東京23区内の介護業界の生活支援業務やマンション管理、清掃等の仕事のマッチングを開始しました。

国内の労働市場における人材不足は深刻化しており、パーソル総合研究所によると2030年には644万人の人材が不足すると推計されています(※1)。しかし、総務省の調査(※2)では、65歳以上の就業希望者は207万人と数多くいる一方、「年齢制限」「仕事の種類」「場所・時間」など、条件面で自分に合う仕事を見つけられていない人も多くいるといわれています。
このようなシニアの「はたらく」をめぐる環境の課題は、どのようにして生まれるのでしょうか。
「高齢者の住まいと介護・医療を考える」をコンセプトに、シニアに関するさまざまな情報発信を行っている「高齢者住宅新聞」の代表取締役社長 網谷 敏数氏と、パーソルイノベーションの戸田 一樹(「アライクワーク」事業責任者)に話を聞きました。
――慢性的な「人材不足」が叫ばれる中、シニア層の活躍に期待する声が大きくなっていますね。
網谷氏:日本の生産年齢人口(15歳以上65歳未満)は減り続ける一方ですが、65歳を超えても、まだまだ元気な人たちはたくさんいらっしゃいます。はたらく意欲のある方に、これからも社会貢献をしていただきたいという声が高まるのは、必然の流れだと思います。

戸田:同感です。人材不足の解消には、女性の活躍推進や外国人材の活用などさまざまな方策がありますが、特に少子高齢化が進む日本では、シニアの活躍が必要不可欠といえます。

網谷氏:彼らが社会に貢献できることはたくさんありますし、シニアがやりがいを感じることは、彼ら自身の介護予防にもなるかもしれません。そうすると国の医療費や介護費の削減にも繋がるので、政策としても、シニアの社会参画は非常に重要なテーマだと考えています。
受け入れ側の業務を可視化することが、シニア活躍への第一歩
――シニアの方々には、はたらく意欲をお持ちの方が多いのでしょうか?
網谷氏:会社を定年退職した方々から、「何かやりたい」という声を聴くことは少なくありません。しかし、その声が顕在化しているかというと、まだそこまでとはいえないのも事実です。時間の余裕ができたとしても、定年まで仕事一筋だったがために自宅周辺地域に知り合いがいなかったり、交流の機会がないというケースも散見されます。そんな状況下で自分に何ができるのかが、分からないのだと思います。
戸田:「きっかけが欲しい」という声は、シニアの方々からよくお聞きします。「〇〇さんにお願いされたから、仕方がないからやってやるか……」というような、ある種の“建て前”があると動きやすく、内心は、そのようなお願いをありがたく感じている方も多いですよね。
網谷氏:声に出さなくても、潜在的に「地域や社会に貢献したい」という想いをお持ちの方は多数いらっしゃる。その声を吸い上げるための仕組みが必要だと思います。
戸田:また、一口にシニアといっても、いろいろな就業ニーズがあります。シニアのニーズでいうと、特に交通の便や体力などの事情から、「家から職場までの近さ」を気にする方もいます。就業時間についても、フルタイムではなく一日数時間のお仕事を望まれている方も多いのですがそのようなはたらき方の仕事を、企業側がまだ生み出せていないのが実態といえます。

――企業側もシニアの活躍を期待しているけれど、準備が整っていないということでしょうか。
網谷氏:私は介護事業者の方とお会いすることが多いのですが、慢性的な人材不足の中で、シニアの手を借りたいという声は増えていると感じます。しかし、単に「人が足りないから入れよう」という考えで採用を進めても、きちんとした仕事を用意できなければ就業者とのマッチングが成立しませんし、一度は就業しても、長続きせずに終わってしまうでしょう。
それを避けるためには、人を採用する前に「いま自分たちはどんな仕事に、どのくらいの人手が足りないのか」を洗い出すことが必要です。一部の事業者では、業務の見える化をして「コア業務」と「ノンコア業務」が何かを見極めたり、テクノロジーを活用できる業務はないか、アウトソーシングできる業務はないかなどを精査する動きも出てきました。このように、新たな人材が活躍できる仕事を整えたうえで、人材募集をしていく必要があります。
戸田:シニアに限らず、企業側が“ダイバーシティ”を受け容れる環境整備が重要ですよね。現在就業している社員にはない属性の方がはたらくとき、どんな人に、どんな仕事を任せられるのか、しっかり考えていかなければいけません。
最近、介護業界では、ほかの業界からの転入者が増えているそうです。新たな出会いが増えているいまだからこそ、そのような課題と向き合うチャンスでもあります。

介護業界の内と外で、変化が求められている
――介護の現場では、ホスピタリティが重視される仕事も多いですよね。仕事内容を紐解くのは、簡単なことではないようにも思います。
網谷氏:「寄り添い」や「ふれあい」、「笑顔」というような、報酬にどう結び付けて良いか分からない要素はたしかにあります。それらは大切にしながらも、たとえば、サポートによって「食事ができるようになった」、「歩けるようになった」など、エビデンスで分かるような仕組みを仕事の評価としても取り入れていこうという動きは、すでに本格化しています。
厚生労働省が告示した2021年の介護報酬改定では、「エビデンスに基づく科学的介護の推進」が謳われており、今年は“科学的介護元年”ともいわれています。
――その動きが本格化すると、エビデンスをデータとして管理する必要も出てきますね。
網谷氏:はい、それも事業を支える大事な仕事になるでしょう。介護業界の中に、介護専門職ではない仕事が生まれてくると、新たな人材も参画しやすくなりますし、異業界の知見も活かせるかもしれませんね。

――さらに別の観点を挙げると、地域共生型社会(※)をつくることも、より良い介護を実現するために重要なポイントといわれています。
(※)世代や分野を超えて繋がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会
網谷氏:要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活といった面を、地域で一体的に支えていくのは、とても重要なことだと思います。
ただ、その社会づくりのモデルは、なかなか見出しにくいのも事実です。日本には1700以上の市町村がありますが、各自治体それぞれの答えがあるんです。その地域事情に即した社会でなければいけません。
戸田:はたらくという観点でこの問題を考えると、先ほど申し上げたような「家と職場との距離の近さ」は、シニアが地域でいきいきと過ごすための大きな要因だと思っています。これまでシニアは「支えられる」側という印象が強かったと思いますが、まだまだ元気でしっかりされている方は多いので、それぞれの地域で「支える」側になれると良いですね。
「アライクワーク」が取り組む課題
――そんな中、「アクティブシニアの力で人材不足を解消する」を掲げた「アライクワーク」が誕生しました。

網谷氏:人材サービスを展開する企業が、シニア領域の重要性を説くことは珍しくありません。しかし、事業として取り組んでいるのは、ごく一部に過ぎませんでした。ですので、アライクワークのことをお聞きしたとき、「いよいよ、本格的にはじまったな」という印象を持ちました。非常に意義のあるサービスなのでどんどん進めていただきたいですし、私たちもご協力できることがあれば力になりたいです。
先ほども申し上げたように、シニアの就労は、受け入れ側の課題が多いのが現状です。その点、アライクワークは採用支援だけでなく、業務の改善や見直しを事業の柱として掲げていますよね。これは絶対に必要なことだと思います。

戸田:受け入れ側の業務改善をしながら、その成功事例を少しずつ広げていきたいです。そのためには、現場の事情を理解しながら、すでに事業所ではたらいている方々にいかに負担をかけずに仕事のやり方を変えていけるか、そして、業務改善をすると何が良くなるのかを示していかなければいけないと感じています。
網谷氏:ぜひ、現況に風穴を開けてほしいです。決して簡単な道のりではないと思いますが、ぜひ長い目で取り組んでいただきたいと思います。
戸田:ありがとうございます。まずは事業者の方々に並走しながら、現在の業務状況が良いのか悪いのかを、しっかりと見える化することに取り組んでいきます。ゆくゆくは事業者の方々が自立して業務改善や採用ができるようになれば、シニアが活躍できる社会に近づくと考えています。
網谷氏:シニアの社会参画については、高齢者住宅新聞もすでに事業者向けのオンラインイベントを行ったりしていますが、今後も積極的に取り上げていきたいと思います。少子高齢化社会を生き抜くためには、さまざまな人や組織が総力を挙げて頑張らなければいけませんね。
*「アライクワーク」サービスページはこちら
(※1)出典:パーソル総合研究所「労働市場の未来推計2030」
(※2)出展:総務省「就業構造基本調査」(平成24年)